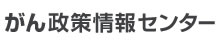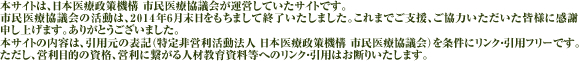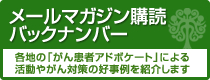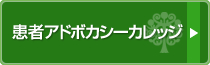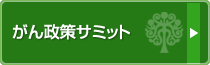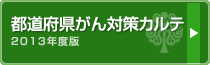| 応援メッセージ 超党派の議員連盟「国会がん患者と家族の会」代表世話人の尾辻秀久議員、事務局長の梅村聡議員をはじめ、多くの国会議員から、サミット開催に際し応援メッセージが届けられました。尾辻議員は手紙、梅村議員はビデオレターで、各地の患者関係委員や患者会の活動にエールを送りました。 |
 |
| 「患者の声を政治に届けて」 国会がん患者と家族の会代表世話人 参議院議員 尾辻秀久さん |
私とがん政策サミットとのおつきあいは、初回の2009年からになります。故山本議員と立ち上げ、がん対策基本法の成立後開店休業状態にあった議員連盟「国会がん患者と家族の会」の再開をお約束したのも、昨年秋のがん政策サミットの勉強会の場でした。あれ以来、がん対策推進協議会の議論は常に注目しております。
議連については、事務局長を引き継いでいただいた梅村聡議員と一緒に、皆さんのご活動の支援ができるよう、具体的な話し合いを進めているところです。また、この度は、国のがん対策推進基本計画について、皆さんで議論されていると聞いております。それはまさに基本法の精神に則った、患者さんががん政策を作っていくという姿であり、ぜひその成果をお教えいただければと思います。がん対策はまったなしで取り組むべき課題の一つであり、私のライフワークです。今後も超党派で取り組んで参りますし、ぜひ、患者さんの声を政治に届けてください。
| 「がん対策はどの政局でも超党派で推進」 国会がん患者と家族の会事務局長 参議院議員 梅村 聡さん |
私は大阪の選挙区で故山本たかし議員のいわば“後任”として参議院議員になりましたが、山本さんにこう言われたことがあります。「いまの政治はそのときのトピックにいろんな政治が飛びつく。社会保障や医療、がんの問題は誰が腰を据えて議論するのか」。
今回、がん議連をもう一度やろうと思ったのは、山本さんの言葉を思い出したからです。がんの問題は、どんな政局になろうと、やっていかなければならないことだと思います。
いよいよ来年からがん対策推進基本計画が2期目に入ります。新しい基本計画の中で、再発がん、希少がん、がん難民の問題にしっかり取り組んでいかなければならない。また、働く世代のがんが大きな問題になっています。就労支援まで含めたがん対策は次の基本計画で大きな課題になるのではないかと思っています。
議員連盟は、来年度予算の問題もありますので、随時開催していきたいと思います。ぜひ皆さん気軽に国会のほうに足を運んでください。
がん対策基本法 過去5年間のまとめ
がん対策推進協議会の役割と新5カ年計画について
特別パネルディスカッション
がん対策推進協議会の役割と新5カ年計画について
特別パネルディスカッション
| 検診受診率アップ、相談支援など問題山積 各ステークホルダーの連携がカギ |
 |
| パネリスト(上段左から)門田守人さん:厚生労働省がん対策推進協議会 会長・大阪大学副学長、鈴木健彦さん:厚生労働省がん対策推進室 室長 モデレーター(下段左から)松本陽子さん:NPO法人愛媛がんサポートおれんじの会理事長、眞島喜幸さん:NPO法人PanCANジャパン理事、花井美紀さん:NPO法人ミーネット理事長 |
最初に取り上げられたのは、「どうすればがん検診受診率がアップするのか」という質問です。厚労省がん対策推進室室長の鈴木さんは、「子宮頸がん、乳がん検診は、85歳以上では非常に低い一方で、35歳~45歳の受診率は40%近い。また企業で取り組むと検診受診率は5割を超えた。どこをターゲットにアプローチしていくかを決め、検診が必要だという風潮を作っていくことが大事ではないでしょうか」と発言しました。
また、がんに関する教育については、がん対策推進協議会会長の門田さんが重点的に取り込みたい項目の一つに列挙。「人間は生きて必ず死ぬ。何らかの形で自分のこととしてがんや病気で死ぬことがあり得るのだということを子供のときから教育の中で知っておく必要があるのではないか」と強調しました。
「がん登録については国民的議論が必要」
 |
| パネルディスカッションの様子 |
相談支援に関しては、今年度、厚労省の予算メニューの中に、ワンストップで患者・家族の相談に乗る病院外の相談機関「地域総括相談支援センター」の設置が入っています。シンポの中で、7月現在、10県が同センターの設置を予算化していることが明らかになりました。患者関係委員でNPO法人ミーネット理事長の花井美紀さんは、ピアサポーターの標準プログラムの作成も予算化された点に触れ、「税金を投入して養成されるからには、医療機関とどう関わっていくのか、チーム医療の中で位置付けることも必要ではないでしょうか」と強調しました。
がん登録についても門田さんが、「わが国全体のがんがどうなっているかというデータがない状態。番号制にでもして、検診を受けているかどうかも含めた医療データの集積し、将来の患者さんの治療に役立てることが重要。皆さんのご意見を聞かせていただいて、がん登録の制度構築に反映していきたい」と話しました。
最後に、患者関係委員でNPO法人愛媛がんサポートおれんじの会理事長の松本陽子さんが、こうディスカッションをまとめました。「皆さんのご意見をうかがって、次の5年間、将来の患者さんのためにも役立つ計画を作っていきたいと思いますので、これからもご協力ください」。
【第2部】
がん対策を動かす仕組みを学び合う~“四位一体”型の議論と意見集約の手法
がん対策を動かす仕組みを学び合う~“四位一体”型の議論と意見集約の手法
|
「 政策スケジュールに合わせて効果的な要望を」
 |
| 前村聡さん:日本経済新聞社東京本社編集局社会部記者 |
来年度から始まる次期がん対策推進基本計画は、ほとんどの内容が予算に関連するのに、がん対策推進協議会は非予算関連であるかのようなスケジュールを組んでいます。予算関連は通常は7月がギリギリのデッドラインですが、計画の骨子もまとまっていない危機的状況。せっかく政策プロセスに関わるがん対策推進協議会に患者関係委員が入っているわけですから、政策決定のスケジュールに合わせて声を上げてほしいと思います。
実は、現在の菅政権では、政策決定プロセスが患者さんなどにはよく分からないまま、例えば子宮頸がんワクチン接種対策に厚生労働省のがん対策推進室の1年間分相当の予算がつくようなところがあります。逆にいえばいろんなパイプが使える。いろんなチャンネルを活用して、政策決定のプロセスを見極めつつ、がん患者に必要な政策を実現していっていただければと思います。
| 実践編 「現状を把握しよう~がん患者意識調査2010年~患者さん1400人回答結果報告」ランチョンセッション |
|
「調査結果をアドボカシー活動に活用しよう」
2009年に引き続き、2010年もがん患者意識調査を実施しました。調査には、1446件の回答をいただきました。がん医療に対する満足度については、約5人に1人が不満足と回答しています。「精神面に対するサポートが不十分」、「治療や医療サービスの情報が少ない」との回答が上位にあがり、ここから精神面のサポートや相談のニーズが明らかになりました。
治療費用については、7割以上が「負担が大きい」と回答し、5.7%が経済的な理由で治療を中断・変更しています。
データを活用する際には、回答者の特徴や調査方法などを考慮する必要があります。この調査に関しては、がんに関連する患者団体の方に実施した調査で、回答者は診断から5年以上10年未満の方が多いという特徴がありました。いろいろなデータを合わせて数字で根拠を示すことでさらにアドボカシー活動が進みます。「がん患者意識調査2010」の結果も活用していただけたらと思います。
ワーク 1~3
| 課題解決への7つ道具で必要な活動を明確化 情報交換をしながら課題と解決策を共有 |
 |
| ワークの資料 |
「相談支援センターが機能していない」「医療費に無頓着な医師が多過ぎる」「情報不足による不安を解消する場がない」
ワーク1では、患者関係者4グループ、議員関係者2グループ、行政担当者、医療関係者各1グループに分かれて、ワーク2では参加者がみんな一緒になって情報交換を行いながら、「患者の悩みを解決する体制」をテーマにした課題・問題と阻害要因について話し合いました。
「患者の悩みがなくなる」があるべき姿・理想とすると、課題・問題として挙がったのは、主に、「情報のありかが知られていない」「十分な情報が提供されていない」「受け手が情報を消化できない」の3点です。その阻害要因として、「PR不足」「出し手と受け手の意識のミスマッチ」「制度ありきの組織」「相談に対応できる人数が少ない」「提供側の認識不足と受け手としての意識不足」が指摘されました。
活動カードを記入し実際のアクションを
 |
| ワークの様子 |
最終目標は、ワークショップを具体的な活動につなげることです。誰が、何をどのようにアクションを起こすのか、アドボカシーワークブック・ツールキット編にある7つ道具の6番目である「活動シート」を作成すると、ワーク3で作った戦略設計シートをより具体化できます。
「具体化することによって初めてアクションにつながるのではないでしょうか。活動カードは、PDCA(計画、実行、評価、改善)サイクルを考慮していますから、評価による見直しもできます。アドボカシーワークブックをじっくり読んで活用していただけたらと思います」。がん政策情報センタープログラムオフィサーの内田亮が、そう参加者に呼びかけ、ワークショップを締めくくりました。その後、参加者から2日目の感想発表と当機構の埴岡健一のコーディネイトによる2日目の振り返りがありました。
※肩書きは当時のものです。